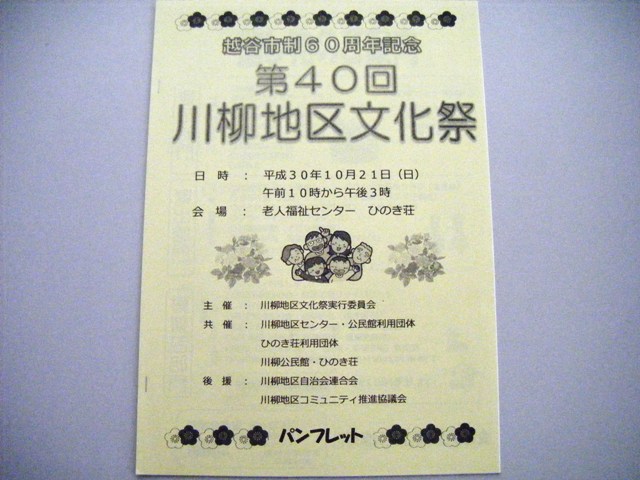施設長の橋本です。
平成18年からスタートさせた「なごみ和太鼓祭」も今年で13回目を迎える事ができました。
このお祭りは、「地域に根差した地域貢献を」としてスタートさせましたが、回を増すごとに地域コミュニティーの皆さんや中学校、お馴染みの演出ボランティアの皆さんなど地域ぐるみでの運営になってきていることは、感謝であり、嬉しい限りであり、この川柳地区の秋祭りとして根差す事ができたのではないかと思っています。
舞台装飾の協力・・・越谷市立光陽中学校美術部
装飾は、昨年に引き続き、光陽中学校美術部の峯(ミネ)先生をはじめ、美術部部員の皆様による作品です。
華やかなダリアの花が祭りの雰囲気を彩り、華やかで素敵な空間を演出しております。
光陽中学校の美術部の皆様、ありがとうございます。


☆美術部コメント☆
「この舞台装飾は「秋」をテーマにデザインを考えました。秋の花の中でもひときわ華やかに咲くダリアの花をモチーフにしました。ダリアの花は大・中・小の折り紙で花びらを作り、1枚、1枚つなぎ合わせて作りました。時間はかかりましたが、花びらが一つ仕上がる毎に、やりがいと達成感があり、楽しみながら製作する事が出来ました。出来あがった時はとても嬉しかったです。どうぞ、赤やオレンジ、黄色など、色とりどりのダリアの花をお楽しみ下さい。」
今回は、台風24号、25号が続けて来ておりましたのでお天気が心配されましたが見事に晴れ渡り、逆に31℃も気温が上がり、熱中症や脱水を心配するような気候の中での開催となりました。
少しでも祭りの雰囲気が伝わるよう演目をご紹介しますね。
①「なごみ和太鼓」でオープニング
今までで一番少ない人数となりましたが、今年も迫力ある演奏をお届けしました。

②「オハナ¬・クーレイ・アロハ フラダンス」
総勢17名の仲間による全6曲のフラダンスは、優雅で祭りを華やかにしてくれました。
お天気も手伝ってハワイの風を感じる事ができましたよ♪


③川柳こども組み太鼓
地域の公民館で練習している子どもたち・・・晴れのステージに拍手大喝さいでした。

④フレッシュバスケットの歌とダンス
株式会社フジパシフィックミュージックより発売中の「みんなで楽しく介護予防体操DVDレッツリハ」で歌を歌っているボーカルグループのフレッシュフルーツバスケットさん4人組の参加です。
楽しく元気な歌とダンスを届けくれました。
※こちらはYouTubeにアップされたそうです。


⑤阿波踊り「がまっ子連」
南越谷阿波踊りへの参加を中心とした「楽しくなきゃ阿波踊りじゃない!」「阿波踊りが好きなら誰でも参加できる」をモットーにしている皆さんです。
鐘の音や太鼓が鳴り出すとワクワク・・ドキドキ・・しちゃいます。
ちびっこから年配まで大迫力でした♪


⑥バンペーラ フラメンコ
普段は看護師さん・・・趣味で始めたフラメンコ。
なごみ祭りには初参加でしたが、太陽に負けない情熱を振りまいてくれました。

⑦よさこいキッズの皆さんとなごみ職員によるソーラン節
今年は、キッズママが中心に練習をリードして頂きました。
忙しい中一緒に、この祭りの会議にも参加して頂きました。
なごみの高齢者は、どんなにこのキッズの踊りを楽しみにしていることか・・


⑧フィナーレは、もちろん、「なごみ和太鼓」
勤務をしながらなので、全員揃って、練習する事ができず、間に合わせることができるか不安になったこともありましたが、何とか間に合ったようです。
勇ましい姿が力強く、時に激しくダイナミックな演奏でした。


⑨サービス精神
最高の天気ではありましたが、暑過ぎて長い時間外にいることができなかった入居者さんのために太鼓のメンバーが、館内の中庭に移動して、演奏してくれました。


⑩越谷ガーヤちゃんもやってきた・・・

どこの地域も高齢化や人口減少などを理由に昔ながらのお祭りが継続できないという課題を抱えていますが、当施設なごみの郷がある、この川柳の地域も自治会の方の頭を悩ませている問題でもあります。
微力ながら、なごみの郷の職員は、地域の縁の下の力持ちとなり、これからも地域活性化に、人と人の繋がりに、尽力していけたらと思っております。
来年は、また更に地域と共に大々的に開催できるよう職員一同頑張る所存です。
どうぞ、ご期待を!